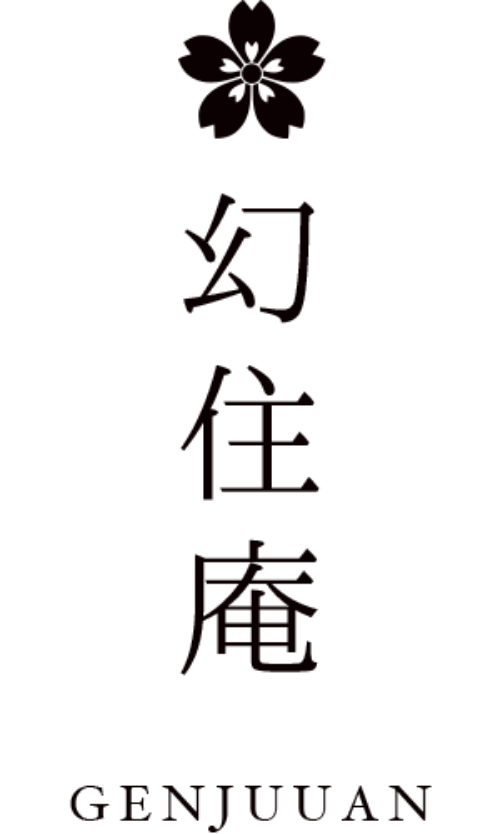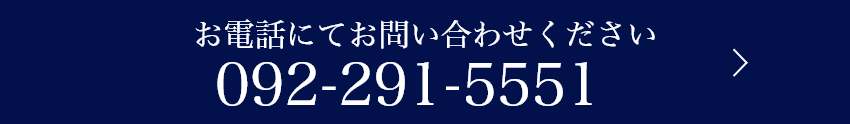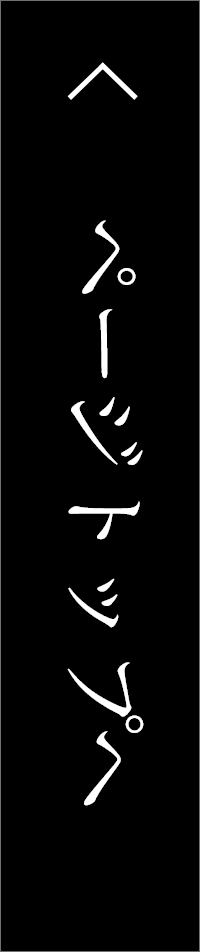SENGAI
仙厓和尚
文化・文政年間(1804年〜1830年) 幻住庵内の虚白院にて聖福寺の名僧仙厓和尚が余生を過ごしました。
名僧仙厓和尚の生涯です。ぜひお読みください(仙厓百話より)
諫言褒美「雲井の梅」
藩主黒田斉清侯は幼少の頃から忠臣井手勘七の硬教育に鍛えられ藩の学者亀井南冥など数人より和漢並びに蘭学を修め、「本草啓蒙補遺」一巻を稿し、別に菊花の絵巻十巻、牡丹の絵巻物数巻を編纂した。就中菊花をこの上もなく愛し、天下の名品を庭園に集めて自ら一かどの研究もし、客を招いては楽しんだ。ある日、今を盛りと咲き乱れる菊園の中に園丁某の飼犬が乱入して幾本かの枝を折ってしまった。
侯は烈火の如く怒って、園丁を手打にすると言い渡した。
これを聞いた仙厓さんは早速夜半庭園を訪ねて、研ぎすました鎌を手に藩主が大切にしていた菊の花を残りなく刈り取ってしまった。
翌日様子を見に御殿を訪ねると大騒ぎである。藩侯の眼は血ばしっている。刀の柄を握った藩主の前に園丁の生命は風前の燈である。和尚は藩侯の前に進んで威儀をたゞし、「お殿様この菊を刈り取ったものは、私、仙厓奴でございます。さあお手打を蒙りましょう。」
「だが一言、人の命と菊の命とどちらが大事でしょうか。しかも藩内は大飢饉で百姓は困っています。これに救いの手ものべず花いじりや、菊見の宴でもありますまい。民百姓あってのお殿様であることをとくとお考え下さいませ。」もとより英明な藩主は、「和尚やりおったわい!」と素直にに自分の非を認めて、「和尚にしてこそ」と感謝し、そのお礼にと藩主が愛していた雲井の梅を賜った。この梅は今も幻住庵の玄関にあって毎春元気のよい若枝を出している。


首斬役人の辞職
夜来の雪で虚白院の庭は白一色におゝわれた。仙厓さんは静かに茶を楽しみながらこの雪景色に陶然と見とれていた。
そこヘ一人の男が訪ねて来た。黒田藩の小役人で、かねてから仙厓さんになんとなく心をひかれていた男である。彼は藩の首斬役人で、しかもその仕事のスリルに不思議な魅力を感じていた。この変態な男のなまくさい自慢話がいつも仙厓さんを微苦笑させたものだ。
「あんたその首斬役人は大抵でやめたらどうな、後生が恐ろしいとは思いならんな。」
「そら又、なしでっしょうかい。命令するたあお殿様で、殺さるゝたァ悪い事したものですバイ。罪やらうらみのあるならーー殿様いたゝりまっしょうたい、私が何んば知りますな。」
「そうばいな、んならよか。そこで一寸あんたい用のあるがその腰の刀であの庭の竹ば一本斬って来ちゃんない。」
男は庭におりて示された竹をめがけて「エイッ」とばかり手なみもあざやかに斬り倒した。とたんに枝もたわわに降りつもっていた雪持ち笹の雪が首斬り役人の頭へまともにビシャリと落ちて来たからたまらない。
「こらァどうか。」
雪を払いながら竹を持って座敦に上がってくるのを見ながら仙厓さんは、ニタリと笑っている。
「あゝその竹にはもう用はなか卜。」
「ヘー?」
「ところで今あんたはびしょぬれになったが仙厓はなしびしょぬれいならんとな。」
「そらァあなた!」
「あっハ・・・竹ば斬れて命令したとはな、仙厓ばい、あんたがびしょぬれいなるわけはないじゃなかな。」
ウウーと手をこまねいていた役人は唸った。そして彼の仏心が奇妙にするどい仙厓の言葉によって芽をふいた。一念発起した彼はたゞちに首斬役を辞職して、ひたすら仏の道を求めて真剣に和尚の教を乞い、後生を懺悔滅罪の行にはげんだと云う。
またから竹の子とらさるな
虚白院の竹やぶに細い筍が頭を出した。一本、二本、三本・・・・・・仙厓さんは毎日、その成長を楽しみにして眺めていた。ところがこの楽しみも、暫時にして無慙に裏切られてしまった。二本、三本、と筍は毎日、根元からポックリポックリと折りとられていった。犯人は裏の石堂川に遊びにくる近所の悪童だ。
「こらァ、ちょっとこっちいきてんない、誰から言いつかってきたとな。ととさんからな。よか、んなら、この絵ばもっていって、ととさんにみせない。」大きな虎の股の下から手を出して筍をとっている図だ。そして賛に日く、
「またから竹の子とらさるな」

壱岐島からきた手水鉢
天保三年、仙厓さんは壱岐島に行脚した。足部村の中村市郎右ヱ門が自然石の手洗鉢を贈った。長右ヱ門は自ら舟を出して和尚を迎え、手洗鉢を積んで博多に帰ってきた。その手洗鉢は幻住庵の庭の仙厓堂の横手にある。
戦災で焼けた休一庵を復興して、昔のままの露地に置きたいものだ。手洗鉢の中に刻した仙厓さんの歌が水を透して幽かに読める。
壱岐より玉へる手洗鉢の石
合甫長 舟に而迎。
龍の宮 我に玉わる玉手箱
風の便りに合ひの浦船
合いの浦船とは合甫の迎え船のことだろう。


絶筆の碑
仙厓和尚は文化八年(一八一一)法席を湛元に譲って虚白院に隠退した。時に六十二歳であった。だがこれは世間並の楽隠居ではなかった。自ら退休の辞を書いて、これからは心のままに大いに教化につとめようと偈を作っておられる。爾後の約二十年間の虚白院時代が仙厓さんの仙厓さんらしい面目を発揮した時代といえよう。
庶民を愛し、庶民の中に溶け込んだ仙厓さんはすっかり博多っ子になりきって、得意の諧謔を交えた歌や描画をもって世間の愚や悪を諷刺したり、様々の奇行や頓智で世人に教誨を与えたりしたのもこの時代のものが多い。仙厓さんが無類の子供好きだったことは有名で虚白院には近所の悪太郎も集まってきた。日々訪うものは、もとより武家、文人墨客、町家の差別なく、その跡をたたなかった。しかし、この楽しげな訪れもよいことばかりではなかった。而もその中には多くの揮毫依頼者が交じっていた。
たのまれれば気安く書く和尚のきさくさをよいことにして、ひきもきらず集まってくるこの依頼者に、さすがの仙厓さんもほとほと困惑した。米屋甚太郎に描いて与えた画の画賛に、
こりゃ甚太郎 虚白院へ行き書きものねだるまいぞ
又合甫長右衛門に与えた歌に、
うらめしやわが隠れ家は雪隠か
来る人ことに紙おいてゆく
和尚も既に八十三歳の高齢になって漸くこの種の書きものに筆をとるのが億劫になってきた。そこで、
墨染の袖の湊に筆すてて書にし愧をさらす浪風
という一首を石工岸田徴平にきざませて庵の傍に立てて”絶筆の碑”とした。天保三年初秋のことである。一説にはともすればきびしい藩の忌弾にふれる惧れに遠慮したためともいわれている。
仙厓和尚のあとを継いだ湛元は本堂の修理がもう一日も猶余のならない程荒廃していたので、なんとか強硬に事を運ぼうとした。これは藩の貧しい財政の故に仙厓和尚以来なかなかききとどけられなかったものだ。湛元の強行策は藩の怒りにふれ、遂に退住を命ざれ大島に流罪となった。それで仙厓さんは再び住職の座につかなければならなくなって百二十五世を継ぐに至った。
時に天保七年、和尚は八十七歳であった。その心痛はいかばかりであったろう。
その冬は寒さが殊に厳しく老体にはなかなか堪え難かった。暗い憂愁と清明な悟りの心が交々和尚の胸中に起伏したことであろう。同藩の碩学亀井昭陽が亡くなった。国学者二川相近も亡くなった。

こんな日々の下で、和尚はしきりに筆を運んで葬送の図を描いた。これは自分の葬儀の模様をかくあれかしと図にしたものである。ここにも生死を超えて、なんのたくらみのなく、いつわりのない人間を語る仙厓さんの大きな姿が投影している。
翌八年、仙厓さんは八十八歳の米寿を迎えた。周囲の者からその祝をと勧められたが、
米の春米の山さし高ければ かまどの烟り立ちもあへせず
と相変わらずのどかに詠みながしていたが、九月微異を得て病床につかねばならなくなった。丁度その頃である。和尚は感得するところがあって、絶筆の名画「大聖不動尊」を描いた。三界の火宅を、辛うじて担い、名状し難い悲痛な面もちで、手にしかと不動の利剣と羂索を握りしめている。その風采は将に仙厓さんの生涯の人生観を渾身の力をこめて描き上げた筆意共に雄渾な一幅である。
仙厓さんが病に臥すや一山の僧侶は勿論日頃親交のある知人など交々来って手篤い看護をしたが、
疲れはて骨と皮とを残す身は
枯木にかかる鶯の声
と自ら既に不起を悟って、法席を弟子の龍岩に譲り、遂に十月七日、病革まるや衣を換え、
来時来処を知る
去時去処を知る
手を懸崖より撤せざれは
雲深くして処を知らず
との偈を書して、多くの人々に惜しまれながら安祥として大往生を遂げられた。
この末期の句の意味を判り易くいえば次のような事ではないか。
(来時知 来処)
人間として生れて出で来る時は、その来る処をちゃんと判っていなければならない。
(去時知 去処)
死んで行く時は、その先ぐらいははっきりと、今此処と見きわめておかねばならぬ。
(不 徹 手懸崖)
然しながら、そうはいってみても、そのままではいかぬ。一度崖から手をはなして谷底へ落ちてみなければ(宗教的に大死一番しなければ)
(雲深不 知 処)
谷底のくわしい様子は上から覗いた位では雲がかかっていて、中々わかるものではない。
こうして一世の名僧仙厓和尚はその生涯を閉じられたのであるが、時のみかど仁孝天皇は「普門円通禅師」の謚をおくって、その徳を称えられた。
お墓は聖福寺山内護聖院にある。