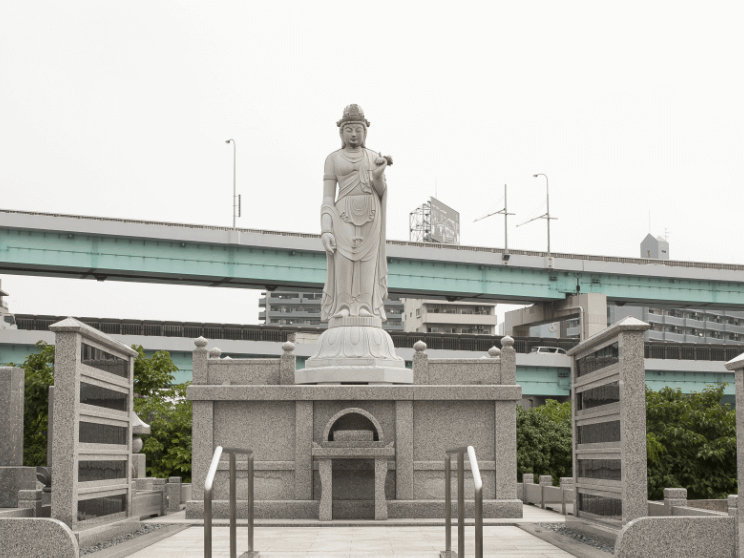ABOUT US
開山無隠元晦
無阻元晦は弘安6年(1283年)に豊前に生まれました。姓は大蔵氏、出生地は田川の弓削田。正安元年(1299年)博多聖福寺明窓宗鑑のもと、戒を授かり、剃髪し僧となります。博多聖福寺は、日本禅宗の初祖と仰がれる明庵栄西が開き、「扶桑最初禅窟」つまり日本で最初の禅寺という由緒を誇る臨済宗の名刹です。 延慶3年(1310年)元に渡って杭州の天目山に登り、天下に名高い中峰明本の元へ参じます。この中峰明本は、その修行の厳しさから死関と称された、高峰原妙の法を嗣いだ人物で、当時稀代の名僧として世に知られていました。今に遺る肖像画を見ると、死関を越えた人物に相応しい特徴が確認できます。高峰原妙のもとで修行するにあたり、その志を証明するために、指に香の束をくくりつけて燃やす燃指を経験した為、左小指がありません。無隠元晦はこの中峰明本の元で、道を究めるべく修行を始めました。正和4年(1315年)に、大悟に至り、中峰明本の法を嗣ぎます。元亨3年(1323年)師である中峰明本が世を去ります。師の死から3年間は天目山に止まり、師の墓所を守りながら喪に服していたようですが、嘉暦元年(1326年)に16年の長きにわたった中国での生活を終えて日本に帰国します。出航は6月22日。玄界灘から博多湾に入ったのは8月のことだと伝わっています。
帰国後は筑前多々良の顕孝寺に住持。延元元年(1336年)に馬出に幻住庵を創建。のちに博多聖福寺の二十一世住持となります。入寺したのは康永元年(1342年)の事だとされています。禅の一大中心地であった福岡の中でも、とくに最古の由緒を誇る寺院であり、そして自らが僧となったこの聖福寺の住持となったことは、無隠元晦にとって感慨深いものであったはずです。聖福寺にあること6年、貞和4年(1348年)京都建仁寺三十二世として迎えられ、翌年貞和5年京都南禅寺二十一世として迎えられています。
南禅寺にあること1年して無隠元晦は退院し、すぐに九州へとかえってきたようです。晩年は静かに暮らしたようで、はっきりとその事実が確認できるのは正平12年(1357年)上野の宝覚寺にあった無隠元晦が中国の天目山以来の友であり、東国の常陸に居を据えて世には出ず、後進の育成に力を注いだ復庵宗己に書状をだしています。この手紙は復庵宗己からの手紙への返信で、2人は帰国後も連絡を取り合っていたようです。その書状では、復庵宗己に、久しぶりに会いたいが叶わないな、と語りかけながら、別れの言葉を述べています。この頃既に、いささか体調を崩していたらしく、そしてこれからちょうど1年後10月17日に無隠元晦はこの世を去りました。しかし、無隠元晦が世を去っても、その存在が忘れられることはありませんでした。100年後の康正2年(1456年)には、後花園天皇から、法雲普済禅師の諡号を下賜されています。